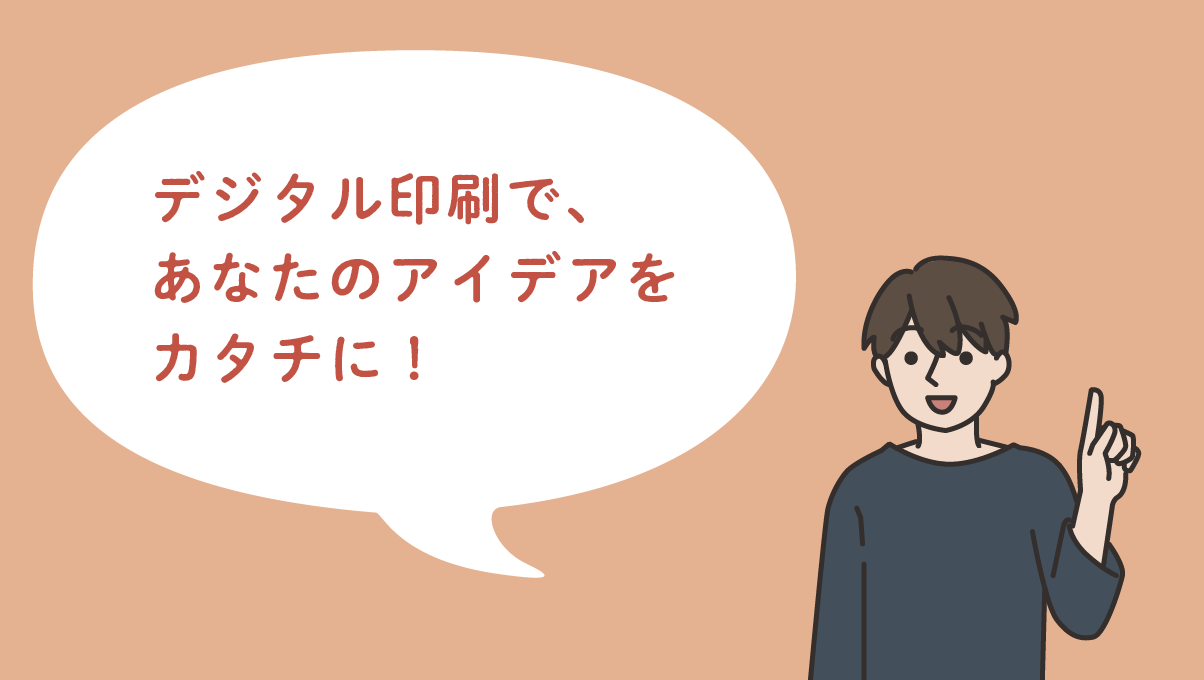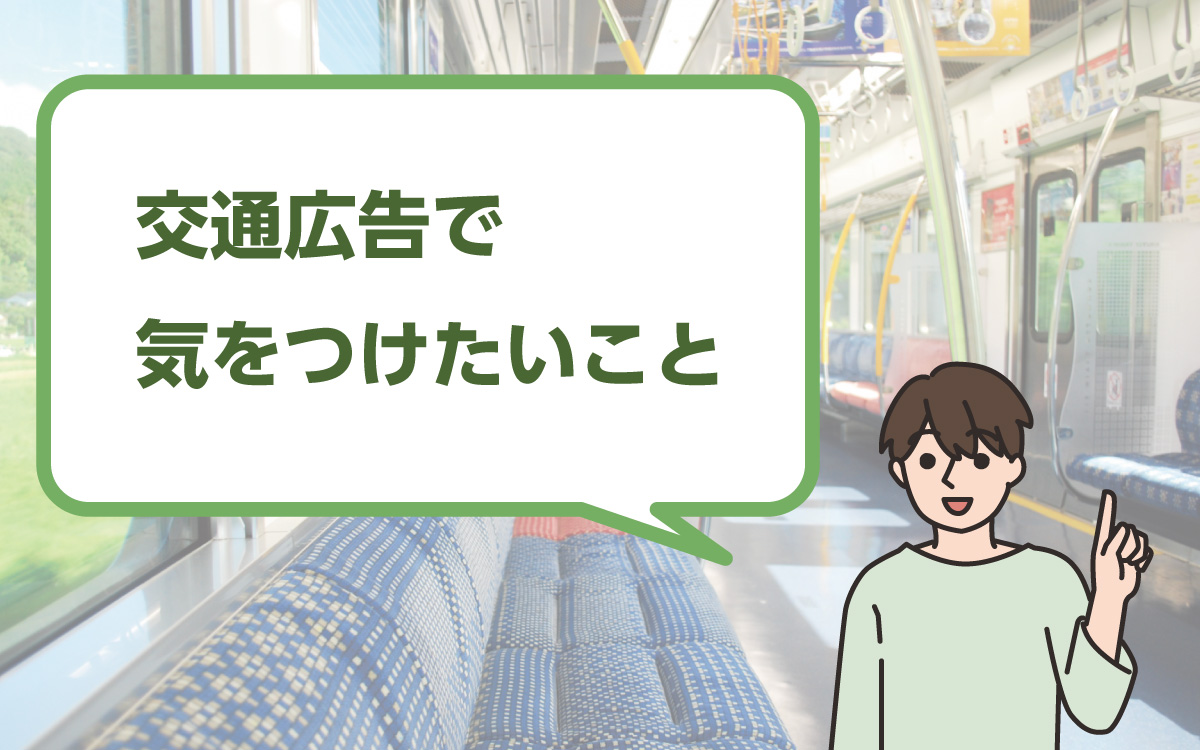色校正時の注意点
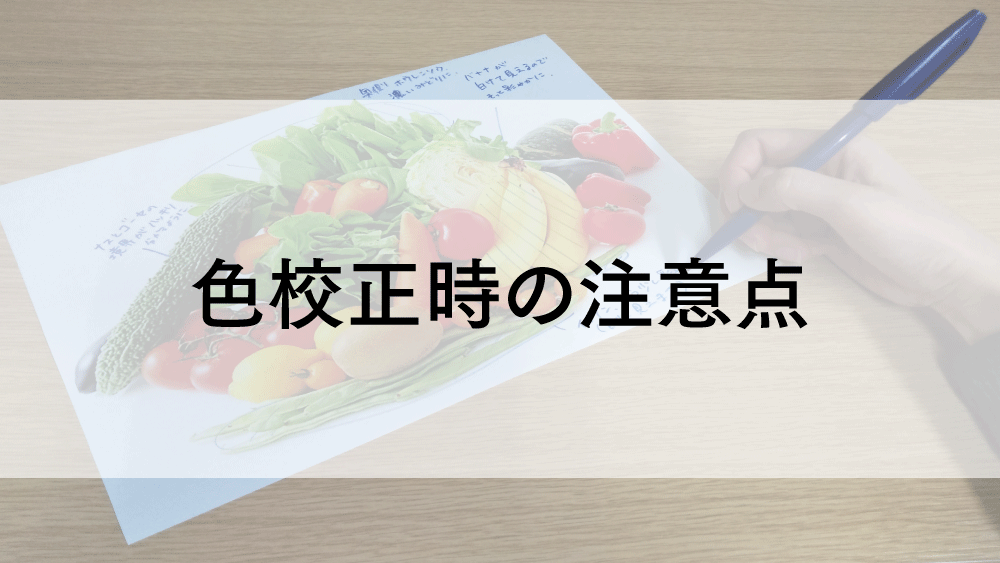
色校正とは、広告などの制作において、イメージを損なわない色味を出すために行われる工程です。
ですが、「色」の見え方には様々な要素が影響を及ぼすことや、個人の感覚による部分もあることなどから、修正指示の伝え方に難しさを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、「前回色見本を見た時と全然違う色に見える…なんでだろう?」「もう少し違う色にしてほしいけど、どういう指示を出したら欲しい色味になるんだろう」と感じたことのある方へ向けて、【色校正をする際の注意点】【指示を出すときの指標】についてご説明します。
ぜひご一読ください。
1.色校正をする際の注意点
色は人それぞれで見え方が異なり、同じ色を見た時の感じ方も違います。また、色の見え方は以下の要素から影響を受けるので注意が必要です。
- 光源(環境)の色味
同じ色でも環境光(室内光、自然光など)によって見え方が異なります。特に自然光が入る部屋で見ている場合は、天気や時間などによって自然光が色に与える影響の具合が変わります。そのため、これらの影響を最小限に抑えるには、できるだけ毎回同じ環境下で色を確認することが望ましく、可能であれば「色評価用」の光源環境下での確認を推奨します。 - 紙種の違い
- 紙の地色の違い
単に”白い紙”といっても、種類によって「黄色っぽい」「青っぽい」など微妙に色味が異なっています。特に紙地の色が出やすい「浅い色」「明るい色」に対して、より影響を与えます。
新聞広告の場合、印刷時には「ざら紙」と呼ばれるグレーがかった地色の紙に出力されますので、色見本が白い紙に出力されたものだと再現できる色味にはどうしても差が生じてしまうことも把握しておきましょう。 - 紙の質感の違い
紙には、「光沢紙」と呼ばれる”光沢感があって表面が滑らかなもの”と、「マット紙」と呼ばれる”光沢感がなく表面が凸凹しているもの”とがあります。
光沢紙に比べてマット紙はインクを吸いやすいため、同じデータを出力した場合マット紙の方が落ち着いた印象に見える傾向にあります。
- 紙の地色の違い
- 色見本の配置
色校正と色見本を比較する際、色見本を右に置くか左に置くかによって、色の見え方が変わることがあります。色見本と校正紙をそれぞれ左右どちらに配置するか統一することで、一貫性を持たせることは可能でしょう。 上記のような色の見え方に影響を及ぼす要素を把握しておくことで、それを踏まえた修正指示が可能になり作業者とのやり取りもスムーズに進められます。
2.指示を出すときの指標
ここからは、色校正の赤字を出すときの指標について、指示の具体例と共に紹介します。- 指標1:明るさ
明るさは、画像や印刷物の全体的な明るさを調整する要素です。
指示の例:「顔全体暗く見えるので、もっと明るく。」 - 指標2:彩度
彩度は、色の鮮やかさを調整する要素です。
指示の例:「ズボンの色、少し彩度抑えて落ち着いたイメージに」 - 指標3:色相
色相は、色の種類やトーンを調整する要素です。
指示の例:「腕時計のベルト部分、少し赤み足す」 - 指標4:コントラスト
コントラストは、明暗差や色の対比を調整する要素です。コントラストが足りない場合、画像は平坦に見えます。
指示の例:「全体がねむい印象なのでコントラスト強めて」
※補足:コントラストが弱くてぼんやりした印象の画像を「ねむい」と言い表すことがあります。 - 指標5:白飛び
白飛びは、明るい部分が過剰に強調されている状態を指します。
指示の例:「白飛びして見えるので、ハイライトを調整する」 - 指標6:黒潰れ
「黒つぶれ」は、暗い部分が過剰に強調されている状態を指します。
指示の例:「シャドウを少し明るくして黒潰れを解消し、革の質感を出す」 - その他
上記のキーワードが複数関わるような修正内容もあります。
指示の例1:「左から2番目の人物の肌色を血色良く健康的にする(右隣の人くらい)」
指示の例2:「フルーツ(特にレモンとリンゴ)が暗く沈んで見える。明るく鮮やかにして美味しく見えるように」
指示内容が何であれ、修正の意図(美味しそうに見せたい、質感を出したい、など)や具体的な範囲・比較対象があると、より伝わりやすく齟齬が少ない修正指示になります。
3.最後に
今回は【色校正をする際の注意点】【指示を出すときの指標】についてご説明しました。
当社は、社内に色評価用の設備(要説明)を有しており、ブレの少ない環境で色見本と校正紙を確認することができます。
色校正に関してお困りの際は、是非お気軽にお問合せください。
なぜ色校正を行うのかついてのコラムはこちら
レタッチ・色調補正についてのコラムはこちら